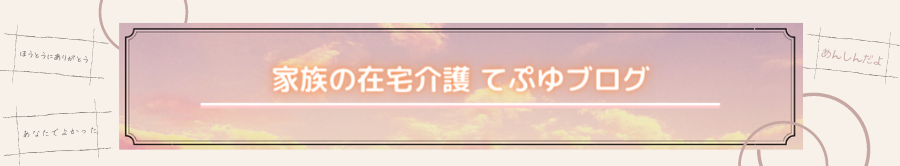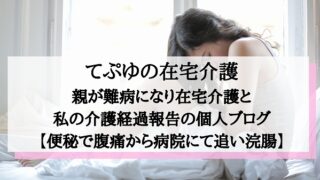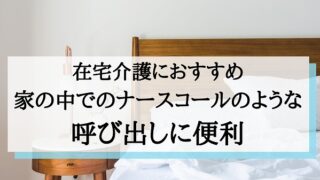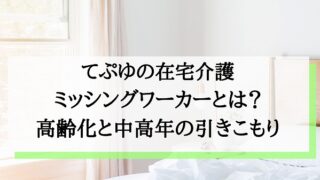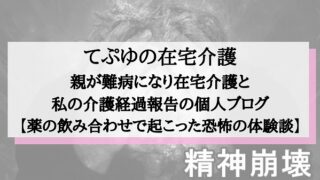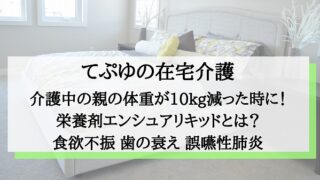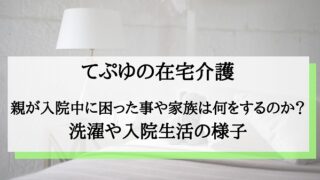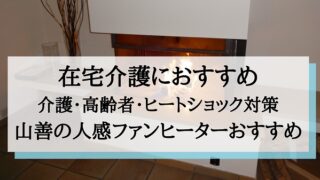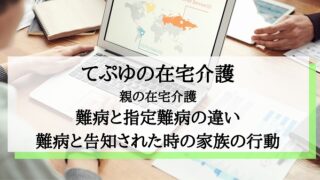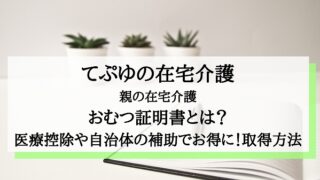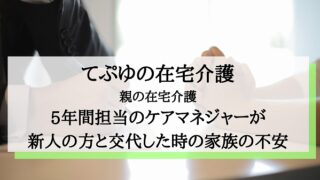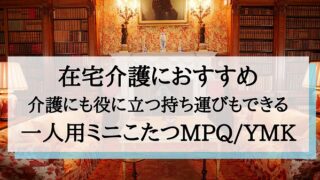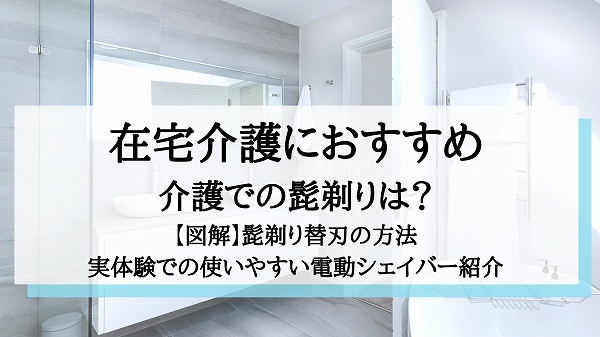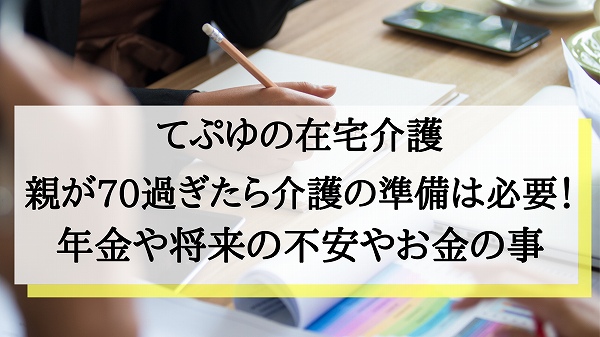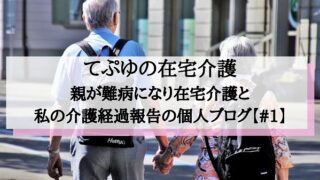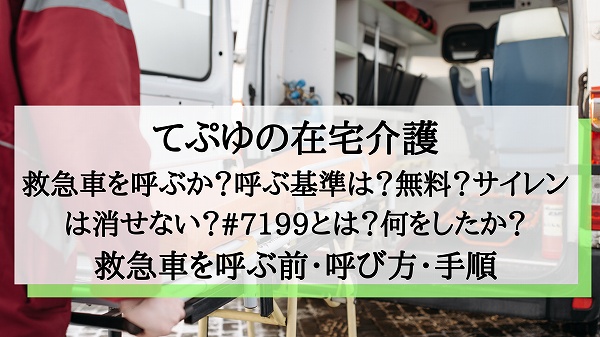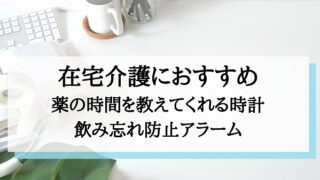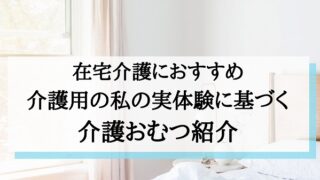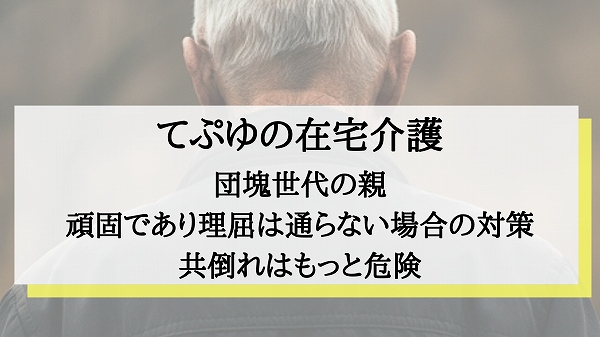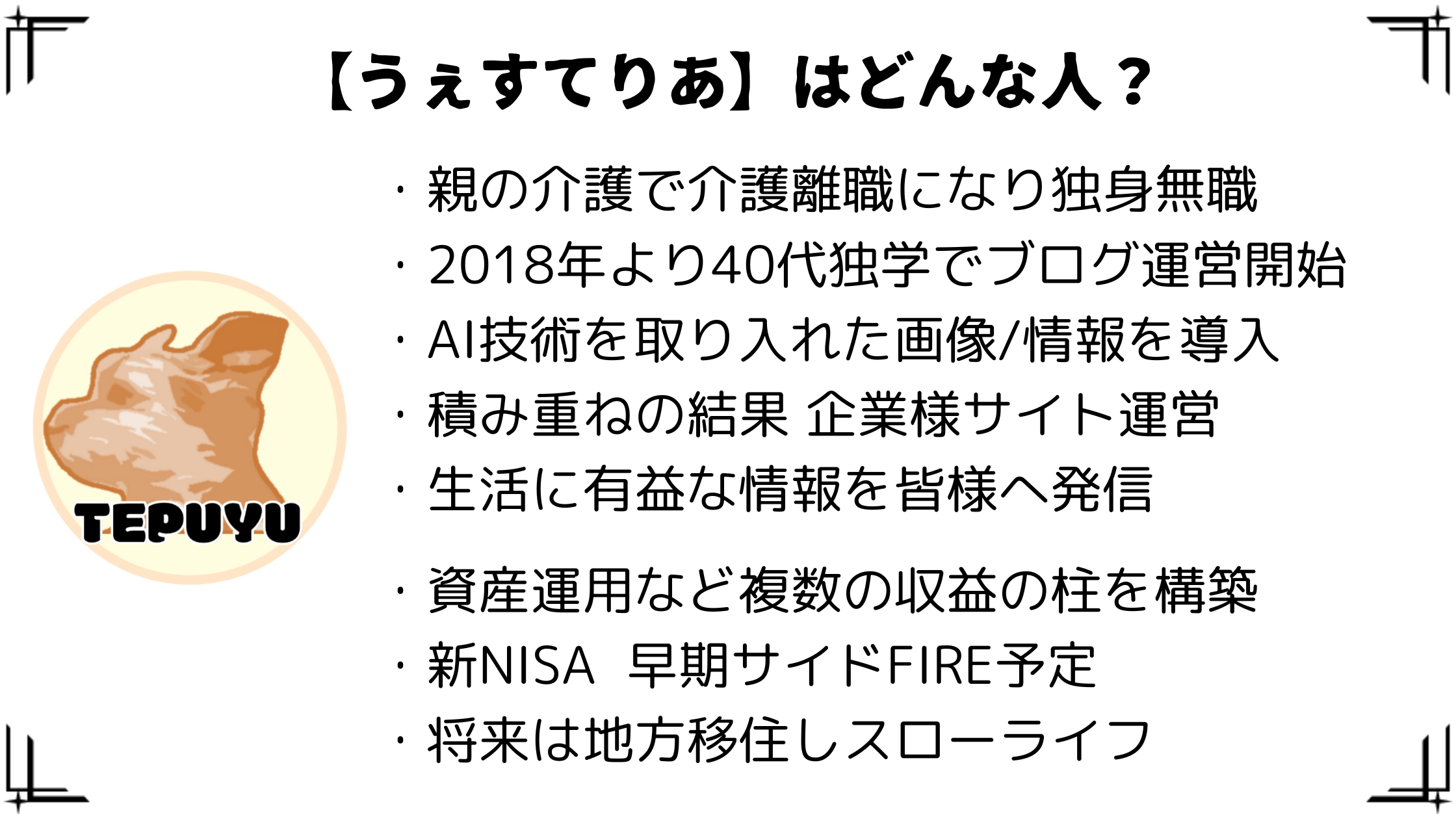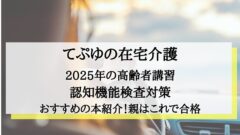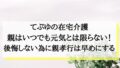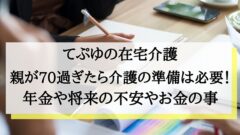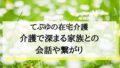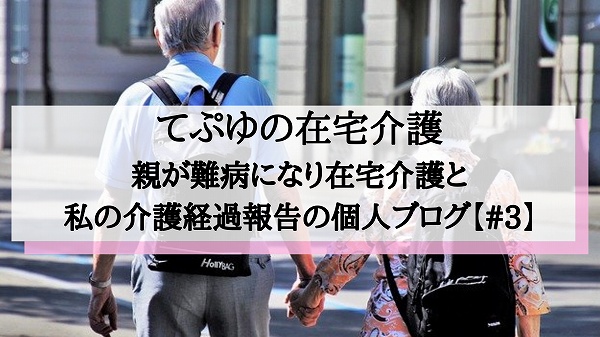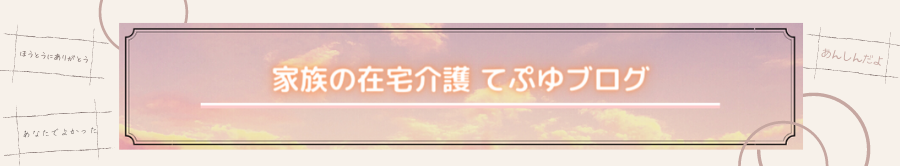介護する側のメンタルが壊れないようにするのが大事!共倒れはもっと危険
介護するにあたって親の考えに困った…
私の親は70代でいわゆる団塊世代と言われるカテゴリーに属すと思います。
その中で私は親の介護という事に直面していて【在宅介護】という状態にあります。
親の介護大変だとは話によく聞きますが実際何が大変なのか?という項目でいろいろある中で今回は団塊世代でよく皆さんも悩まれる【頑固】という問題にフォーカスを当てて記事にして対策や世間やネットの声を交えながら私の体験談などをまとめてみました。
親の介護を考え始めると、「こうしたほうがいい」「こうしてほしい」が通じない壁に直面する場面が多くなります。
頑固な親それは“理屈では動かない壁”かもしれない
特に団塊世代以上の親世代は、価値観・慣習・経験が強く固まっていることが多い傾向に思えます。

私自身の体験からも本当にこの「親の頑固問題」には在宅介護の中でも大きなストレスを溜め疲弊し精神的に参った事柄の一つです。
皆さんも決して一人で悩まずに「こんな人がいる」「私の状況と似ている」「みんな大変んだ!一人ではない」など介護する家族の重荷が少しでも軽くなるようしていきたいですね。
この情報が何かしらのお役に立てれば幸いだとおもいます。
頑固な親における典型的な問題点・背景理解
親が頑固になる背景・心理構造
■加齢・認知機能変化 → 新しい考え方を受け入れにくい
■高齢者はこれまでの経験に基づく価値観を重視しがち、新しい情報に対して「疑い」のスタンスを取ることが多い
■老化に伴う判断力や柔軟性の低下、記憶の混乱が“頑固さ”を助長する可能性
■長年「自分が正しい」「経験がある」立場で生きてきたため、自分の判断を揺るがしたくない心理、自尊心・アイデンティティ維持の傾向
■子から指摘・提案されると「否定された」と感じやすい
■“命令・指示”と受け取ると反発を招く
■防衛・抵抗反応
■身体機能の衰えや老いを自覚し、心理的に「まだ大丈夫」と主張したくなる
典型的なトラブル事例(私の体験談・口コミ・ネット反応から)
明らかなゴミでも必要と取っておいてゴミ屋敷になる(紙袋、包装紙、段ボールなど)
使って無い何年の前のモノ(趣味の物、バック、靴、洋服、置物、食器、布団、貰い物のタオルやシーツなどなど)団塊世代の人は処分する時に決断できないし、こちらの正論を言っても断固として受け入れないから子(介護者)が疲弊・精神的負荷を抱える
実家じまいや庭じまいや墓じまいなどの案件も話し合いが平行線で進まない
「親がデイサービスを拒む」「作った料理をまずいと言って食べない」「あれは嫌だこれをしたい!」など、まるで子供のようにワガママ・反発が目立ち、昔はしっかりした親だったのに…と落胆して疲弊してしまう
「親の言うことを無理に変えようとしたらケンカになる」など葛藤の声
認知症を伴う親が理屈をまったく受け付けず、意味不明な言動をする → 介護者がストレスを重ねる
“無理難題を押し付けてくる”と感じる方も多く、苛立ちや疲労につながる
親は価値観ギャップがありインターネットやAIなど現代技術に不信感を抱いており、若年世代の情報参照を認めないことが対立を生む
親と子の間で“世間の一般常識”が違うため、同じ話題や考え方でも噛み合わないことがよくある
“理屈が通らない”状態で無理に説得しようとする危険性

論破型アプローチの落とし穴
こちらの考えを強く押すと反発を招き、親の考えを指摘すると「否定された」と感じて信頼関係が壊れる場合がありますよね。
そうすると結局親子間で感情的な対立に発展し、話し合い自体を拒絶されるようになりお互い疲弊してしまいます。
その積み重ねがゆくゆく、子(介護者)が疲弊・精神的負荷を抱えるリスクになります。
実際私もこれらの落とし穴にハマりかなり疲弊した事もあり親への寄り添いが無く自己嫌悪になる事も多くあります。
納得させようとする」こと自体がストレスに
「子供が自分の論理で説得しようとする → 親のリアクション予測できず、心身が疲れる
話を重ねるたびにすれ違い・摩擦が積み重なる
介護そのものへのネガティブ感情が強まる
頑固な親への対策“理屈以外のアプローチ”と“環境の調整”
ここからは理屈が通じにくい親と向き合う際に有効と思われる実践的な手法を段階的に私也に整理します。
心理的アプローチ:共感・肯定から入る
■完全に同意しなくても「話を聞く」姿勢を示す
例:「そうか、それは辛かったね」「そう思うこともあるかもしれない」など、まずは気持ちを受け止める
■親の主張・感情を否定しない(正しい/間違いで反論しない)
■小さな妥協点をつくり全体を変えるというより「まずはここだけ一緒にやってみようか?」という提案型をしてすぐに試せること・簡単なことから入る
間接的アプローチ:代替案・第三者の介入
介護保険サービス・訪問ヘルパー・デイサービスなど家族信託・成年後見制度など、将来的な制度設計を見据えておく(親が納得しやすい形で紹介)
活用できる制度・サービスを自然に取り入れる工夫を考える
これは私の親には効果的で第三者(専門家・地域包括支援センター・ケアマネなど)を交え、専門家からの説明・提案として提示すれば、親も聞きやすくなる
環境調整:物理的ハードルを下げ家の設備を変える(手すり、段差解消、見通しの良い間取りなど)親が行動しやすい動線を整備し、「やらざるを得ない状況」をつくる
コミュニケーション技法:言葉・タイミング・形式を工夫
曖昧表現・選択肢型で提案を短く・簡潔に・一度に一つだけ「AかB、どっちがいい?」スタイルで選ばせる
・非言語を使う:一緒に動いて見せる・視覚的に示す
・手紙やメモ、写真などを使って間接的に伝える
・タイミングを見極め機嫌が良い時、疲れていない時に話し、疲れている・反発された直後など避けるようにするだけでもかなり効果は変わります。
親の自己防衛・介護者側のメンタル管理
お互いの感情の“ガス抜き”ルートを確保する
例:定期的な休息・代替介護者の導入・相談相手・コミュニティ・カウンセリング・趣味など
お互いに境界線を引き出来る事・出来ない事を区切り“全部抱え込まない”ように意識しストレスや疲労のサインを無視しない
具体的対策案:ケースごとのアプローチ
A:認知症・判断力低下が背景にあるケース
医療的・判断支援を取り入れ認知症診断・記録をもとに「判断能力に影響が出てきている可能性がある」事を明確にする事でお互いの感情の変化も区別できるようになる
ケアマネ・医師を交えて家族会議を開き行動ベースで支援し生活リズムを崩さずに親が調整選びやすいように選択肢を絞る
B:価値観ギャップ・精神的頑固さが強いケース
趣味・過去の経験と紐づけて提案し「昔あなたが好きだったこと」や「得意だったこと」に寄せて誘導する
仲間や同世代の事例を共有「あなたの世代の人もこういう風に変更した人がいる」など実例を挙げる
小さな成功体験を積ませ小さな一歩 → 成功体験 → 次のステップという感じで少しずつ問題点を改善していく
C:完全拒絶・感情的対立の場合
一時的な距離の確保し話さないままにせず、手紙・メモ・専門家を通じて伝える
完全拒絶・感情的対立の場合にはこの距離や時間をおく事も大変有効です。
将来設計を先に進めておく法的・制度的手段を視野に入れる(成年後見制度・家族信託など)
注意点・落とし穴:対策を行う上で意識すべきこと
親の尊厳を損なわない配慮
「やらされ感」「押し付け」を感じさせない事、説得より“共創”の感覚を持たせ、親の意思決定を取り上げすぎないようにする。
対策を急ぎすぎない・段階的に進める
子(介護者)が焦る気持ちもありますが…一度に全部変えようとしない小さな変化から始めて軌道修正可能にする心持も大事です。
兄弟・家族間の意見の違いに注意
介護観・価値観が異なる家族間で衝突が起こりやすい面、家族間で事前に“介護方針”について共有・合意をとっておくとその時の対処も違って動く事も出来るので話し合いは必要です。
これで揉めるとまた違ったストレスを溜める事になります。
法的・制度的リスクの理解
成年後見制度や家族信託にはコスト・手続き・制約あり
無理な契約・強制はあとで親、自身、家族間での大きなトラブルの火種になる可能性があるので専門家(司法書士・弁護士・行政書士)を交えて慎重に設計
事例・成功例インタビュー(仮設・参考)
実在の現場の口コミや実体験などの意見を私なりにまとめてみました。
Aさん(50代・独身で親を支えるケース):最初はまったく聞き入れなかった親に、小さな“選択肢付き提案”から始めて徐々に受け入れてもらった
Bさん(60代・兄弟間で役割分担したケース):兄弟で介護ポリシーを共有し、ストレス軽減した
Cさん(認知症が進んだ親):医師・ケアマネの説明や資料を使って家族会議を重ね、制度利用を親も納得して導入
など注意点など把握し少しでも対策をしているとしていないでは結果が変わっていきます。
おわりに:理屈で通らない親との向き合い方は「心を通わせる工夫」から

頑固で理屈を通さない親との関係は、決して簡単ではありません。
年齢を重ねるほど、親との会話が理屈では通らなくなる瞬間が増える。
特に団塊世代の親は、自分の生き方や価値観に強い信念を持ち、それを曲げることを“負け”だと感じてしまう傾向がある。(子(介護者)側からすると勝ち負けなんて考えていない)
こちらが正論を伝えても反発や無視で返され、疲弊することも少なくない。
しかし無理に説得しようとすることは往々にして逆効果になります。
大切なのは、親を「変えよう」とせず「受け止める」こと。
私たちができることは親の気持ちに寄り添いながら少しずつ環境を調整し、関係性を崩さない“橋渡し”をすること。
完璧な理解よりも相手のプライドを尊重しながら、少しずつ歩み寄る姿勢が現実的だ。
時には距離を取ることも優しさの一つ。
親を論破するより、安心させる言葉を選ぶほうが関係は穏やかになる。

理屈を超えた「情」でつながること、それが中年期以降の親子関係の鍵かもしれないと感じます。